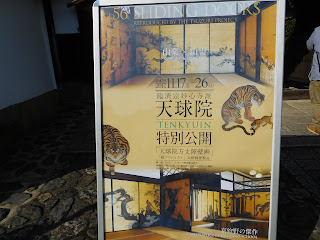等持院は、足利尊氏が天龍寺の夢窓国師を開山として1341年に創建され、足利将軍家の菩提所になっています。写真は等持院の山門です。
等持院は、開山以来、足利家の菩提寺として発展し、北山に大きな寺域を占めていましたが、室町幕府の衰退とともに荒廃していったようです。写真は等持院の西庭の芙蓉池と中島です。庭園は衣笠山を借景として造られたようですが、現在は立命館大学の校舎で眺めを遮られてしまったようです。写真は西庭の灯篭です。
西庭と東庭の間に足利尊氏の墓がありました。
足利尊氏は、後醍醐天皇方に与して鎌倉幕府の滅亡に尽力した後、後醍醐天皇が始めた建武の新政に不満を持ち、後醍醐天皇と対立するようになったようです。そして、後醍醐天皇は吉野に逃れ、南朝を樹立することになります。このように後醍醐天皇と対立した尊氏は、皇女和宮を降嫁させた岩倉具視とともに京都の人から嫌われているようですね。写真は足利尊氏の墓です。
足利尊氏の墓より東側に東庭の心字池、西側に西庭の芙蓉池があり、それらの池にはかつて衣笠山から水が引かれていたそうです。写真は東庭の心字池です。
心字池は滑らかな曲線が強調され、池の周囲にはモミジなどが植えられていました。
心字池の中島とモミジ
書院から見た西庭、石橋の先に見える松が素晴らしいですね。
等持院の散歩を終わります。